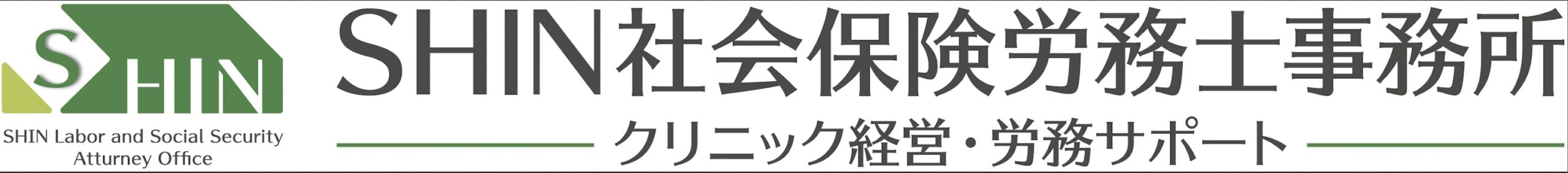「最低賃金アップでも安心!クリニック経営を守る7つの工夫」

STEP0|前提を揃える:最低賃金上昇は“固定費の定期便”
最低賃金の上昇は「毎年届く固定費の定期便」です。逃げられないものだからこそ、先回りして備えることが大切です。
最低賃金が上がれば、当然スタッフの時給が上がります。これは受付や医療事務、看護助手といった職種に特に影響します。しかも、最低賃金に近い人だけでなく、給与の逆転現象を防ぐために全体のバランスを取る必要があります。その結果、クリニックの人件費はじわじわと膨らんでいきます。
例えば時給が30円上がるとしましょう。1日6時間、週5日勤務のスタッフが5人いれば、年間で約23万円の追加コストになります。さらに社会保険料や賞与に波及すると、その影響額はもっと大きくなります。これは「放っておくと赤字に直結する問題」なのです。
だからこそ、賃上げを「コスト増」とだけ考えるのではなく、経営改善のきっかけととらえることが重要です。
STEP1|現状を数値化する:いまの“体温”を測る
まずは現状把握が出発点です。数字で状況を見える化しなければ、正しい判断はできません。
「なんとなく大丈夫そう」では危険です。人件費率、職種別の時給帯、残業時間、離職率などをデータで確認することで、課題が浮き彫りになります。数字は嘘をつきません。
あるクリニックでは、職員の人件費率が収入の55%に達していました。しかし院長は「50%くらいかな」と思い込んでいたのです。実際に数字を出したことで、改善の必要性を認識できました。また、シフトの余剰や不足を見える化すると、余分な残業代や人手不足の実態も明らかになります。
現状を数値化することは、まさに体温を測るようなものです。熱があるかどうかを知ってこそ、薬や治療を考えられるのです。
STEP2|影響額を試算する:3つのシナリオで“腹を括る”
最低賃金上昇がどのくらいのコスト増になるのかを試算することが欠かせません。
試算をせずに対応を後回しにすると、気づいた時には資金繰りが苦しくなってしまいます。シナリオを立てておけば、経営判断に余裕が生まれます。
例えば、最低賃金が30円、50円、80円上がった場合の3シナリオを計算します。それぞれで年間人件費がいくら増えるのか、社会保険料や賞与にどう響くのかを確認します。あるクリニックでは、年間ベースで「30円アップ=40万円」「50円アップ=70万円」「80円アップ=120万円」と試算されました。これを知っているかどうかで心構えは大きく変わります。
シナリオ試算は「最悪を知って備える」ためのものです。備えがあれば、焦らずに対策を打てます。
STEP3|シフト・人員配置の最適化:足りないのは“人数”ではなく“設計”
人件費の膨張を抑えるには、人数を増やすより「配置の最適化」が効果的です。
患者のピークに合わせて人を配置し、タスクを細かく分けることで効率は大きく上がります。
あるクリニックでは、午前のピーク時に受付スタッフを2名から3名に増やし、午後の閑散時間を1名に減らしました。これにより、残業が大幅に減り、患者の待ち時間も短縮しました。また、医療クラークを導入して看護師の業務を軽減し、限られた人数で効率よく回せるようになりました。
足りないのは人数ではなく「設計」です。シフトの工夫で無駄をなくし、同じ人数でより多くの患者を対応できる体制を整えましょう。
STEP4|業務効率化&DX:1分短縮×100件=“時給1人分”の価値
業務効率化とデジタル化は「時間を生み出す投資」です。
1人あたりの作業時間を短縮すれば、同じ時間でより多くの患者に対応できます。結果として残業や追加人員を減らせます。
Web問診を導入したクリニックでは、受付での記入時間が1人あたり5分短縮されました。1日20人なら100分=1人分の労働時間に相当します。これだけで年間約200時間の節約になり、人件費換算で数十万円の削減効果がありました。
「小さな効率化が積み重なれば、1人分の人件費に匹敵する価値になる」。これがDX導入の本質です。
STEP5|収益サイドのテコ入れ:取りこぼしゼロと“選べる単価”
コスト削減だけでは限界があります。収益を増やす視点が必要です。
診療報酬の取りこぼしや加算漏れ、自費診療の説明不足などは、意外と大きな機会損失につながります。
ある内科クリニックでは、栄養指導加算を正しく算定していませんでした。導入後、月に10万円以上の増収につながりました。また、インフルエンザ予防接種の価格を地域相場に合わせて改定しただけで、年間数十万円の収益増を実現しました。
収益の取りこぼしを防ぎ、適切な単価設定を行うことが「守りの経営から攻めの経営」への第一歩です。
STEP6|人事制度・賃金テーブル再設計:“公正感”が離職を止める
賃上げの波を乗り越えるためには、公正な人事制度が必要です。
スタッフが「自分の給与は妥当だ」と納得できるかどうかが、離職率に直結します。
あるクリニックでは、経験年数と役割に応じた3段階の賃金テーブルを導入しました。昇給ルールを明確にしたことで、不満が減り、離職率が下がりました。また、資格取得支援を制度化することで、学ぶ意欲も高まりました。
「公正感」がスタッフのやる気と定着率を支えます。制度設計はコスト増への最大の防波堤です。
STEP7|資金繰り・助成金・90日実行計画:やることを“カレンダー”に落とす
計画は行動に落とし込まなければ意味がありません。
資金繰りを確認し、助成金や補助金を活用しながら、90日間でできる実行計画を立てることで、改善が加速します。
あるクリニックでは「1か月目=現状把握、2か月目=効率化導入、3か月目=賃金テーブル改定」とロードマップを作りました。助成金も併用したことで、費用負担を抑えつつ改革を進められました。
行動計画をカレンダーに落とすことが「机上の空論」から「実行」への第一歩です。
まとめ|最低賃金上昇をチャンスに変える経営へ
最低賃金の上昇は避けられない現実ですが、それを悲観する必要はありません。
①現状把握 → ②影響額試算 → ③シフト最適化 → ④効率化 → ⑤収益強化 → ⑥人事制度 → ⑦資金計画
このステップを踏めば、クリニックは「人件費増で苦しい経営」から「賃上げを成長のチャンスに変える経営」へと進化できます。
変化に対応できるクリニックこそ、患者にもスタッフにも選ばれる存在になります。今こそ一歩を踏み出しましょう。
私自身は開業コンサルティングの他、社会保険労務士と行政書士の資格を有しており、顧問社労士のほかにも、開業支援の経験と調剤薬局経営の経験をもとにクリニック経営でお悩みの院長をサポートし、安定的な経営を支援するためのクリニック経営参謀型コンサルティングもしております。
クリニックの労務・経営・開業サポート クリニック運営参謀
SHIN社会保険労務士・行政書士事務所
医師専用フリーダイヤル 0120ー557ー009
MAIL:ask@shin-silc.jp
www.shin-silc.jp
ご相談、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら