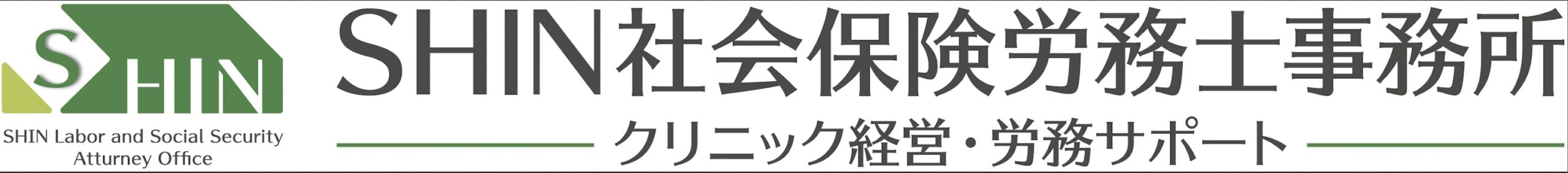クリニックに就業規則なんて無くてもうまくいく。その考え古いです!!
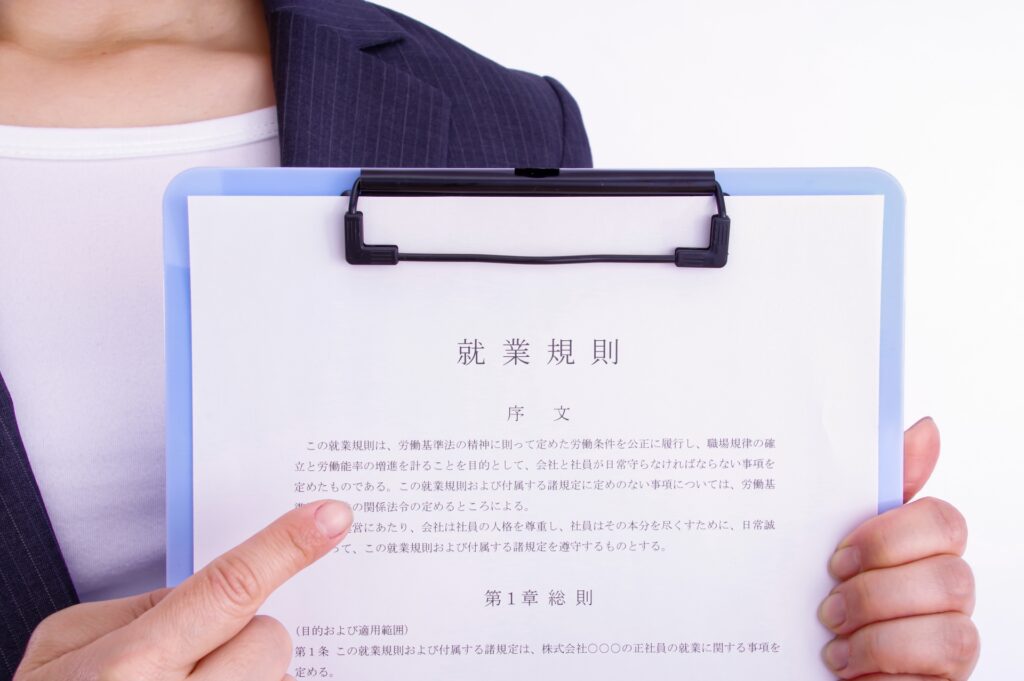
小規模クリニックこそ就業規則が必要な理由
はじめに
「うちは小さなクリニックだから就業規則はいらない」――こう考えている院長先生は少なくありません。
確かに、従業員が10人未満であれば法的な作成義務はありません。しかし、義務がないからといって不要というわけではないのです。
むしろ、小規模クリニックだからこそ、就業規則の整備が経営の安定とスタッフの安心につながります。今回は、就業規則を作らないことで生じるリスクと、作成することで得られる具体的なメリットについて解説します。
なぜ小規模クリニックは就業規則を作らないのか
小規模クリニックで就業規則が整備されていない主な理由は、労働基準法第89条により「常時10人未満の労働者」であれば作成・届出義務がないためです。法違反にならないため、経営者側が「必須書類」と認識していないケースが大半です。
就業規則未作成の背景
- 法的義務がない:10人未満の事業所には作成・届出義務がありません
- 密なコミュニケーション:少人数のため、ルールを明文化しなくても日常業務が回ると考えられがちです
- 業務の優先順位:診療業務が優先され、規則作成が後回しになります
- コスト意識:作成にかかる時間や費用を避けたいという意識も働きます
しかし、「義務がない」ことと「不要である」ことは全く別の問題です。口約束や曖昧な運用だけでは、トラブル発生時の対処が困難になり、助成金申請の機会も失うことになります。
就業規則未整備で起きる具体的なトラブル
実際に就業規則が未整備のクリニックで起こりうるトラブルは、経営を揺るがすほど深刻なものばかりです。
1. 懲戒処分が行えない問題
業務怠慢やハラスメントなど、問題のあるスタッフがいても懲戒処分の根拠がなければ適切な対応ができません。安易に解雇すれば不当解雇として訴えられるリスクが高まります。
2. 未払い残業代請求トラブル
残業代の計算方法や支払い規定が明確でないと、退職後に多額の未払い残業代を請求されるケースが頻発します。証拠がなければクリニック側が不利になることも少なくありません。
3. 労働条件の認識違い
賃金や労働時間など基本的な条件が明文化されていないと、「聞いていた条件と違う」というトラブルが頻発します。口頭での約束は証拠として残りにくく、争いの原因になります。
4. 賞与・退職金を巡るトラブル
賞与や退職金の支払い基準が就業規則にない場合、退職予定者への支払い条件を巡って争いになることがあります。特に退職金については、大きな金額が動くため紛争に発展しやすいのです。
5. 服務規律の不明確による職場秩序の乱れ
会社のルールが曖昧だとハラスメント対策が不十分となり、職場環境の悪化やスタッフのモラル低下を招きます。結果として優秀な人材が離れていく原因にもなります。
6. 助成金申請ができない
多くの助成金制度では、就業規則の整備が受給条件となっています。未整備だと申請すらできず、本来受け取れたはずの支援を逃すことになります。
7. 解雇を巡る争い
解雇や懲戒解雇の基準がないと、不当解雇として訴訟リスクが高まります。裁判になれば時間もコストも膨大にかかり、クリニックの評判にも影響します。
これらはどれも経営リスクを高める深刻な問題です。たとえ法的義務がなくても、就業規則の整備と周知はトラブル防止の上で極めて重要なのです。
10人未満でも作成を強く勧める理由
法的な位置づけ
労働基準法第89条では作成・届出義務は「常時10人以上」に限定されていますが、10人未満でも作成は違法ではなく、むしろ厚生労働省も積極的に作成を推奨しています。
小規模事業所であっても就業規則を作成し周知すれば、「就業規則としての法的効力」が認められます。これにより、労使トラブル時の処理基準や各種ルールの明確化が可能になるのです。
実務上のメリット
労使間の誤解・紛争の未然防止
労働条件や勤務時間、休暇などのルールを明文化することで、トラブルの予防効果が格段に高まります。「言った・言わない」の水掛け論を防ぐことができます。
職場秩序の維持とスタッフの安心感向上
ルールが明確であれば、スタッフは安心して働くことができます。モチベーションや信頼感が向上し、定着率の改善にもつながります。
助成金申請や社内管理体制の整備
多くの助成金では就業規則の整備が条件となっています。早期に整備しておくことで、必要な時にすぐ申請できる体制が整います。
将来的な成長への備え
いずれ従業員が10人を超える可能性を考えれば、早めに作成しておくことで将来の負担を軽減できます。慌てて作るよりも、余裕を持って整備する方が質の高い規則ができます。
就業規則を作成した場合の具体的な効力
就業規則を適切に作成・周知すれば、次の3つの重要な効力が発生します。
1. 新規採用者の労働条件を規律する効力
就業規則に定めた労働条件(賃金、労働時間、休暇、服務規律など)は新規採用者に自動的に適用されます。雇用契約書に記載がなくても就業規則の内容が優先されるため、採用時の説明が効率化されます。
例えば、試用期間を3か月と定めていれば、個別契約で6か月とした場合でも就業規則が優先される可能性があります。
2. 既存スタッフの労働条件を合理的に変更できる効力
合理的な内容の変更であり、かつスタッフに周知すれば、既存スタッフの労働条件を就業規則に沿って変更できます。ただし、不利益変更の場合は慎重な対応が必要で、不当と判断されると効力が認められません。
この効力により、事業環境の変化に応じた柔軟な労働条件の見直しが可能になります。
3. 労働契約の最低基準を定める効力
就業規則は、法律や労働協約、個別労働契約に対して労働条件の最低基準を示します。これよりスタッフに不利益な条件は無効となり、就業規則の基準が適用されます。
例えば、パートスタッフの時給が個別契約で低く設定されていても、就業規則でより高い時給が定められていれば、就業規則の基準が適用されます。
効力発生の条件
これらの効力は「就業規則が合理的であること」「スタッフに周知されていること」が前提です。労働基準監督署への届出自体は効力発生の直接条件ではありませんが、法令遵守の観点から重要です。
これらの効力により、職場のルールや秩序維持、トラブル時の対応基準を明確化でき、経営リスクの大幅な軽減につながります。
まとめ:小規模クリニックこそ就業規則を
従業員10人未満のクリニックには就業規則の作成義務はありません。しかし、義務がないからといって作らなくてよいわけではないのです。
むしろ、小規模だからこそ一人ひとりのスタッフが重要であり、その労働条件や職場のルールを明確にしておくことが、信頼関係の構築と経営の安定につながります。
就業規則は「トラブルが起きてから作る」ものではなく、「トラブルを未然に防ぐために作る」ものです。クリニックの成長と、そこで働くすべての人の安心のために、今からでも就業規規則の整備を検討してみてはいかがでしょうか。
労務管理や就業規則の作成でお困りの際は、社会保険労務士など専門家にご相談ください。クリニックの実情に合わせた適切な規則づくりをサポートいたします。