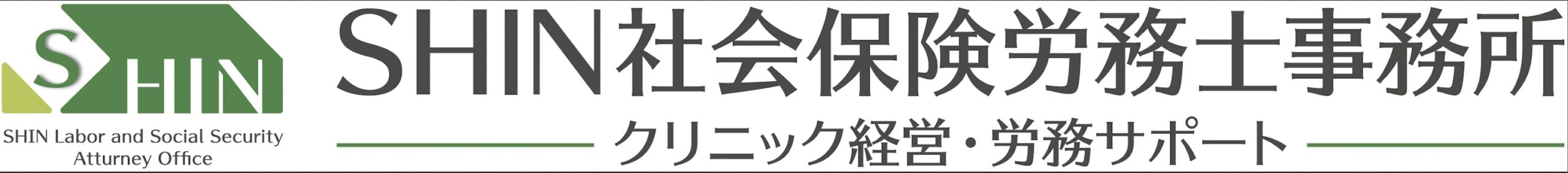分院長契約を正しく結ぶための完全ガイド|医療法人の役員報酬契約で安心経営を実現する方法

医療法人の分院長や理事を「役員報酬契約」で迎える際、契約の作り方を間違えると後々大きなトラブルに発展することがあります。でも大丈夫です。正しい手順と知識があれば、安心して分院展開を進められます。
この記事では、分院長契約を適切に結び、労務トラブルを未然に防ぐための実務手順を、社会保険労務士・行政書士の視点からわかりやすく解説します。
この記事でわかること
✓ 「役員契約」と「雇用契約」の違いが明確にわかる
✓ 分院長契約を切り替える際の具体的な手順がわかる
✓ 労働基準監督署や裁判で問題にならない契約書の作り方がわかる
✓ 日々の運用で気をつけるべきポイントがわかる
なぜ分院長契約では「役員」と「雇用」の区別が重要なのか
分院を展開する際、分院長や理事を「役員(理事)」として迎えるケースが増えています。ところが、契約書では「役員」としていても、実際の働き方が「雇用されている社員」と変わらない場合、後から「自分は労働者だった」と主張されるリスクがあります。
よくあるトラブル事例
- 分院長から「未払い残業代がある」と労働基準監督署に相談される
- 社会保険の加入手続きを遡って求められ、多額の保険料負担が発生
- 退職時に「不当解雇だ」と訴えられる
これらのトラブルの原因は、「契約書の内容」と「実際の働き方」がズレていることです。
重要なのは、「役員」という名称ではなく、実際の働き方(実態)で判断されるという点です。この基本を押さえれば、安心して分院長契約を結ぶことができます。
なぜこのようなトラブルが起きるのか?
実は、分院長契約のトラブルには「専門家側の知識不足」が関係していることがあります。
雇用契約と役員契約の法的根拠の違い
- 雇用契約:労働基準法が根拠 → 社会保険労務士の専門分野
- 役員契約(委任契約):民法が根拠 → 行政書士・弁護士の専門分野
多くの社会保険労務士は労働基準法には精通していますが、民法(委任契約)を深く理解していないケースが少なくありません。そのため、役員契約を作成する際に「雇用契約の延長」のような内容になってしまい、後々トラブルに発展するのです。
当事務所では、社会保険労務士と行政書士のダブルライセンスを活かし、労働法と民法の両面から適切な分院長契約をサポートいたします。
基礎知識:役員契約と雇用契約は何が違うのか
まず、役員契約と雇用契約の違いを整理しましょう。
役員契約(委任契約)の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的な位置づけ | 民法の「委任」契約。医療法では「理事=業務執行機関」 |
| 立場 | 法人の経営を担う立場。指揮命令を受けない |
| お金の呼び方 | 役員報酬(定期同額が原則) |
| 税金 | 所得税・住民税は課税。消費税は非課税 |
| 社会保険 | 常勤役員は原則加入 |
| 就業規則 | 適用されない(役員用の内規を別途作成) |
雇用契約の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的な位置づけ | 労働基準法に基づく契約 |
| 立場 | 法人に雇われて働く労働者。指揮命令を受ける |
| お金の呼び方 | 給与・賃金(時間や成果で変動可) |
| 税金 | 所得税・住民税は課税。消費税は非課税 |
| 社会保険 | 被用者として加入 |
| 就業規則 | 適用される |
最大のポイント
**役員は「経営する側」、雇用者は「雇われて働く側」**という立場の違いです。
もし役員なのに、出退勤の時間を細かく管理されたり、残業を指示されたり、時間に応じて報酬が変動したりすると、「実際は雇用されている労働者では?」と判断される可能性が高くなります。
注意!よくある「名ばかり役員」のパターン3つ
善意で運用していても、次のようなケースでは「実態は雇用」と判断されるリスクがあります。
パターン①:契約書の言葉が雇用契約そのもの
NGな表現例
- 「勤務時間は9時から18時まで」
- 「残業が発生した場合は別途支給」
- 「給与支払い日は毎月25日」
これらは雇用契約で使う言葉です。役員契約では「職務」「報酬」「任期」といった言葉を使います。
パターン②:報酬が時間や日数で変動している
NGな設定例
- 週3日勤務なら月額30万円、週5日なら50万円
- 診療時間に応じて報酬を増減
- 月ごとに報酬額がバラバラ
役員報酬は「職務の責任に対する対価」であり、原則として定期同額(毎月同じ金額)である必要があります。
パターン③:出退勤を厳しく管理している
NGな運用例
- タイムカードで毎日打刻を義務付け
- 遅刻・早退を記録して注意
- シフト表で勤務時間を細かく指定
役員は自らの裁量で職務を遂行する立場です。出退勤の厳格な管理は「指揮命令下にある労働者」とみなされる要因になります。
安心して進める!分院長契約の正しい切り替え手順【8ステップ】
ここからは、雇用契約から役員契約へ切り替える、または新たに分院長を役員として迎える際の具体的な手順を解説します。
Step 1|現状の確認(実態チェック)
まず、現在の契約や働き方を確認しましょう。
チェックポイント
- □ 出退勤の管理はどうなっているか?
- □ 残業の指示や時間管理をしているか?
- □ 報酬は毎月定額か、それとも変動しているか?
- □ 就業規則を適用しているか?
簡易判定 「時間で報酬が変わる」「出退勤を厳しく管理」「就業規則を適用している」に当てはまる場合は、役員契約として不十分です。改善が必要です。
Step 2|法人内での正式な決定(理事の選任)
役員として正式に迎えるには、法人内での決議が必要です。
必要な手続き
- 社員総会で理事選任の決議を行う
- 各行政庁に変更届けを行う
- 稟議書や決裁書で記録を残す
- 職務権限表で役割を明文化する
この手続きを踏むことで、「正式に法人の経営を担う役員として迎えた」という証拠が残ります。
Step 3|役員報酬の設計(税務・労務の両面から適切に)
役員報酬は、税務上も労務上も適切に設計する必要があります。
設計のポイント
- 定期同額で設定する(原則として毎月同じ金額)
- 金額は「職務の責任に見合った対価」として説明できるように
- 報酬の決定は理事会で行い、議事録を必ず残す
- 賞与的な変動報酬は原則として避ける
毎年の見直しも大切 役員報酬は事業年度ごとに見直すのが一般的です。その際も理事会で決議し、議事録を残しましょう。
Step 4|契約書の作成(雇用の言葉を使わない)
役員契約書は、雇用契約書とは全く別のものです。
契約書に必ず入れる項目
- 当事者(法人と役員の名前)
- 職務内容(業務執行・経営に関する職務)
- 任期(定款との整合性を確認)
- 報酬(定期同額で、課税関係も記載)
- 指揮命令を受けないことの明記
- 秘密保持・個人情報保護
- 解任・辞任の手続き(理事会決議が必要)
- 善管注意義務
- 反社会的勢力の排除
契約書の文例(重要部分)
第○条(職務の遂行)
乙(役員)は、甲(医療法人)の理事として、甲の指揮命令を受けることなく、
自らの裁量と責任において職務を遂行する。
乙には就業規則は適用されない。このように、**「指揮命令を受けない」「就業規則の適用除外」**を明記することが重要です。
Step 5|規程・運用ルールの整備
契約書を作っただけでは不十分です。日々の運用ルールも整備しましょう。
整備すべきもの
- 就業規則の適用除外を明記し、役員本人に通知
- 役員用の内規・決裁フロー・職務権限を整備
- タイムカードやシフト管理は原則不要(必要な場合は「参考記録」として位置づける)
運用のコツ 出退勤の記録が必要な場合(安全配慮の観点など)も、「指示」ではなく「自主的な記録」として扱い、残業管理や給与計算には連動させないことが大切です。
Step 6|本人への説明と同意書の取得
契約内容を変更する場合、本人にしっかり説明し、理解と同意を得ることが不可欠です。
説明すべき内容
- なぜ役員契約に切り替えるのか(法的根拠・背景)
- 役員と雇用の違い
- 報酬の決め方
- 働き方がどう変わるか
- 社会保険や税金の取り扱い
必ず書面で同意を取る 口頭での説明だけでなく、同意書に署名・捺印をもらい、説明時のメモや質疑応答の記録も残しておきましょう。
Step 7|証拠の保管(後日のトラブル防止)
万が一トラブルになった際、適切な手続きを踏んだことを証明できる書類を残しておくことが重要です。
保管すべき書類
- 社員総会議事録
- 稟議書・決裁書
- 役員契約書(原本)
- 本人の同意書
- 役割定義書・職務権限表
- 役員名簿
- 役員報酬台帳
- 説明時の資料やメール
これらをファイルにまとめ、PDF化してバックアップも取っておくと安心です。
Step 8|定期的な点検(年1回)
契約を結んで終わりではありません。定期的に見直しましょう。
点検項目
- □ 実際の働き方が「雇用化」していないか?
- □ 報酬は定期同額を守れているか?
- □ 新たに就任した役員も同じ扱いになっているか?
- □ 契約書や規程に不備はないか?
年に1回、理事会のタイミングなどで見直すことをお勧めします。
労働基準監督署や裁判で不利にならないための4つのコツ
せっかく適切に契約を結んでも、日々の運用で実態がズレてしまうと意味がありません。
コツ①:名称より実態を重視
「役員」という肩書きがあっても、実際に時間管理や指示命令をしていれば「雇用」とみなされます。日々の運用が契約書通りになっているか、常に意識しましょう。
コツ②:言葉遣いに気をつける
契約書や社内文書で「勤務」「給与」「残業」といった雇用契約の言葉を使わないようにしましょう。「職務」「報酬」「業務」といった言葉に統一します。
コツ③:専門家と連携する
税理士・社会保険労務士・行政書士が連携して、税務・労務・法務の観点から契約を設計することが理想です。
コツ④:記録を残す習慣
議事録、決裁書、同意書、説明資料など、あらゆる場面で記録を残す習慣をつけましょう。これが後々の「守り」になります。
失敗事例から学ぶ:こうなると危険です
事例A:役員報酬なのにシフト制で残業指示
状況
分院長を役員として迎えたが、実際にはシフト表で勤務時間を指定し、残業も指示していた。
結果
労働者性が認定され、未払い残業代と社会保険料の遡及請求が発生。法人に大きな負担がかかった。
事例B:報酬を月ごとに増減
状況
役員報酬を「今月は忙しいから多めに」「来月は少なめに」と変動させていた。
結果
税務調査で定期同額の原則違反と指摘され、法人の損金として認められず追徴課税。
事例C:就業規則で懲戒処分
状況
役員契約のはずが、遅刻や業務ミスを理由に就業規則に基づいて懲戒処分を行った。
結果
手続き違背を理由に処分が無効となり、慰謝料請求にも発展。
よくある質問(Q&A)
Q1. 役員報酬には税金がかかりますか?
A. はい、所得税・住民税は課税されます。ただし消費税は非課税です。法人の経費(損金)として認められるには、定期同額であることが原則です。
Q2. 役員は社会保険に加入する必要がありますか?
A. 常勤の役員は原則として社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。非常勤や限定的な職務の場合は個別判断となりますので、専門家にご相談ください。
Q3. 役員にもタイムカードは必要ですか?
A. 原則として不要です。ただし、安全配慮や診療運営上の参考として記録する場合は、あくまで「自主的な記録」として位置づけ、指揮命令や残業管理の証拠にならないよう注意が必要です。
Q4. 役員が診療業務もする場合はどうすればいいですか?
A. 経営(役員としての職務)と診療(専門職としての業務)の役割を明確に文書化しましょう。診療面での連絡は「業務連絡」の範囲にとどめ、使用従属性(雇用関係)が生じないよう配慮することが大切です。
まとめ:正しい分院長契約で安心の医療法人経営を
分院長や理事を役員として迎える際は、契約書の作成だけでなく、実際の働き方や日々の運用まで一貫して「役員」として扱うことが重要です。
成功のポイント ✓ 契約書で「指揮命令を受けない」「就業規則の適用除外」を明記
✓ 報酬は定期同額で設定し、理事会で決議
✓ 出退勤の厳格な管理は避ける
✓ 説明と同意を丁寧に行い、記録を残す
✓ 年1回、契約と実態のズレがないか点検
正しい知識と手順を踏めば、分院長契約は決して難しいものではありません。安心して分院展開を進め、持続可能な医療法人経営を実現しましょう。
SHIN社会保険労務士・行政書士事務所のサポート
当事務所では、医療法人の分院長契約・役員報酬契約の設計から運用まで、トータルでサポートいたします。
主なサービス内容
- 役員契約書の作成・リーガルチェック
- 雇用契約から役員契約への切り替え支援
- 役員報酬設計と税務・労務の両立アドバイス
- 就業規則・役員内規の整備
- 理事会議事録等の文書作成支援
- 定期的な労務点検・コンプライアンス診断
こんなお悩みはありませんか?
- 「分院長を迎えたいが、契約の結び方がわからない」
- 「現在の契約が本当に適切か不安」
- 「過去に結んだ契約を見直したい」
- 「労務トラブルを未然に防ぎたい」
医療法人特有の労務・人事の課題を、20年以上の医療業界経験と社会保険労務士・行政書士の専門知識でサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください
当事務所は、クリニックに特化した社労士・行政書士事務所です。
ご相談・お問い合わせ
SHIN社会保険労務士・行政書士事務所
お問合せはこちら問い合わせ
または
医師専用フリーダイヤル 0120-557-009